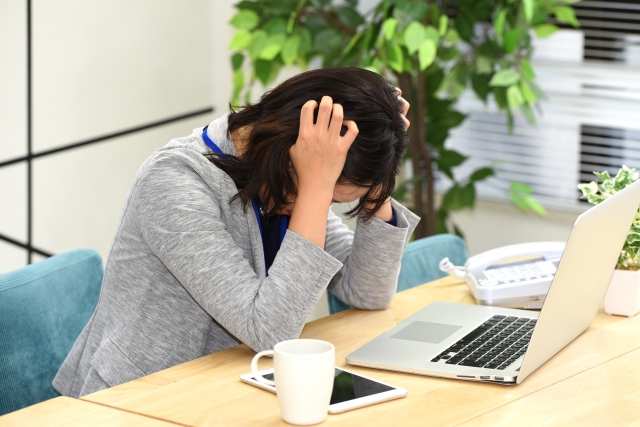
企業にとってパワハラ対策は極めて重要な課題ですが、その対応に頭を抱えている人も多いのではないでしょうか?パワハラ被害については様々な事案が報道され、企業にとって大きなマイナスイメージになることは誰もが理解しているハズです。
しかし、多くの職場では未だにパワハラが残っているのが実情だといえるでしょう。パワハラについては、その実態や被害者に対すケアについては論議されることはあるものの、加害者の心理状況やケアについてはあまり論議されていません。
私は様々なパワハラ事案を担当してきましたが、実は加害者へのケアも大きな課題です。この記事ではパワハラの定義に加え、加害者に対する対処法についても記載しています。パワハラ対策に興味のある方は、是非読んでみてください。
そもそもパワハラとは

そもそもパワハラとは、どういった言動を指すのでしょうか。実は職場のリーダーの中にも、パワハラに該当する言動を正しく理解していない人が多いのが実態です。
パワハラの対処法を考えるには、まず、その言動を正しく理解することが不可欠です。ここでは、厚生労働省が示すパワハラの定義について紹介します。パワハラについて正しく認識しましょう。
以下引用:2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!
優越的な関係を背景とした言動
まず1つ目の定義は「優越的な関係を背景とした言動」です。職場で業務を遂行するに当たって、当該労働者が行為者に対して抵抗や拒絶できない関係性を背景に行われることを指します。
わかりやすく言えば「上司」や「先輩」、「業務に精通した者」などがあげられます。一般的にはパワハラは上司・部下の関係で行われることをイメージしがちですが、それだけではありません。
部下から上司、同僚から同僚に行われるパワハラもあります。例えば、新たに昇格した役職者に対して、仕事に精通した部下が仕事を教えないといった事例です。
この場合、仕事を教えてもらうには、上司であっても部下には抵抗できない関係にあります。つまり、実質的には部下が優越的な立場にあるといえ、十分にパワハラとして定義付けられます。
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
2つ目の定義は「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」です。一般的な社会通念に照らし合わせ、その言動がが明らかに業務上の必要性がないもの、若しくはその態様が常識を逸脱する状況を指します。
ここで難しいのが「業務上必要な指導であったか否か」といった点です。上司が部下を指導することは「業務上必要な言動」となります。つまり、その指導方法が適切であったかが問題です。
例えば、社員を立たせたまま30分以上指導する行為はパワハラと認定される可能性が高いと言えます。指導する言動は丁寧であったとしても、30分以上立たせる行為は、労働者の身体に苦痛を与えるものであり、「相当な範囲」を越えているとみなされるでしょう。
労働者の職場環境が害されるような言動
3つ目の定義は「労働者の職場環境が害されるような言動」です。行為者の言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が及ぼされることを指します。
悪影響が及ぼされるか否かの判断については、同様の状況下で一般の労働者がどう感じるか、すなわち「平均的な労働者の感じ方」が重要です。
パワハラの6つの類型を理解しよう

前項ではパワハラの定義について紹介しましたが、具体的にどういった言動がパワハラに当たるのでしょうか。厚生労働省では、パワハラを6つのパターンにカテゴライズしています。
ここでは、パワハラの6つの類型について紹介します。どういった言動がパワハラに該当するのかを理解し、判断基準を明確にしておきましょう。
以下引用:2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!
身体的な攻撃
最もわかりやすいパワハラ行為が「身体的な攻撃」だといえるでしょう。殴る・蹴る・モノを投げるなどの行為は全てパワハラに当たります。
極めて悪質なパワハラ行為であり、未だに横行していることを信じられない人もいるでしょう。しかし、誰も見ていない所で、被害者が申告しないと踏んで暴力行為を繰り返している事例もたくさんあります。
例外的に「誤ってぶつかった」場合は対象とはなりませんが、わざとぶつかる輩がいるのも事実です。あり得ないではなく「あるかもしれない」と考えて職場を観察することが大切です。
精神的な攻撃
言葉による暴力である「精神的な攻撃」には、脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言が該当します。厚生労働省で示している具体例を以下のとおりです。
- 人格を否定するような言動を行う。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む。
- 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う
- 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う
- 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信する
ただし、以下の行為は必要な指導(注意)であり、パワハラには該当しないとしています。
- 遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をする
- その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をする
つまり、どういた場面・どういった方法(口調)で注意したのかによって、判断が分かれるところになります。大切なのは、労働者に注意を促すものであったか否かであり、注意と称して当該労働者に苦痛を与える行為はパワハラです。
人間関係からの切り離し
「人間関係からの切り離し」には、隔離・仲間外し・無視などがあげられます。まるで、子供同士の「いじめ」のようですが、大人であっても「いじめ」は存在しているのが実態です。厚生労働省では以下の様態をパワハラとしています。
- 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする
- 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる
なお、以下の様態はパワハラには該当しないとしています。
- 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施する
- 懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせる
例えば、社員が仕事について質問しても、聞こえないフリを繰り返す行為はパワハラに該当します。パワハラについて無知な社員は「大声をあげたり、暴力を振っていないのだからパワハラではない」と主張するでしょう。
しかし、当該社員は精神的な苦痛を感じており、就業できない状況に追い込まれることから立派なパワハラになります。また、研修と称して長期間にわたり社員を乖離する行為もパワハラに該当する可能性が高いので注意が必要です。
過大な要求
社員の能力を超えた「過大な要求」には、業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制及び仕事の妨害などがあげられます。厚生労働省では以下の様態をパワハラだとしています。
- 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる
- 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する
- 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる
ただし、以下の様態についてはパワハラには該当しないとしています。
- 労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる
- 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せる
職場の管理者・役職者は社員のレベルに合わせて役割分担を行います。しかし、社員が想定するレベルに達していない、成果が上がらない場合に「過大な要求」が起こりがちです。
非常に判断の難しいところですが、行為者に悪意があったか否かがポイントとなります。また、必要な指導・研修を行っていたか否かも判断する要素の1つです。
過小な要求
前項とは真逆の「過小な要求」には、業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること及び仕事を与えないことがあげられます。厚生労働省では以下の様態をパワハラだとしています。
- 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
- 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない
ただし、以下の様態についてはパワハラには該当しないとしています。
- 労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減する
「過小な要求」も「過大な要求」と同様に、社員が管理者・役職者の考えるレベルに到達できない場合に起こりがちです。この時、当該社員に対する指導・研修の有無・内容等が争点となることは言うまでもありません。
個の侵害
私的なことに過度に立ち入ることは、「個の侵害」としてパワハラに当たるとされています。厚生労働省では以下の事案をあげています。
- 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする
- 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する
ただし、以下の様態についてはパワハラには該当しないとしています。
- 労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行う
- 労働者の了解を得て、当該労働者の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促す
ここでポイントとなるのが「機敏な個人情報」の取り扱いです。個人情報保護の観点からも、日頃から社員に対しては「機敏な個人情報」を暴露しないよう周知・徹底することが不可欠だといえるでしょう。
パワハラ防止法とは

労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が施行され、中小企業を含む全ての企業がパワハラに対して、有効な措置を行うことが義務付けられました。
- 事業主の方針等の明確化および周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるパワハラ に関する事後の 迅速かつ適切な対応
- 併せて講ずべき措置
労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!
企業はこれらの措置を講じないと、法律違反となり罰則が課せられます。したがって企業としてもパワハラを起こす社員は「阻害要因」であり、早急な対応が求められています。
パワハラが顕在化しない理由とは

職場には明らかにパワハラが横行しているにも関わらず、顕在化しない職場も少なくありません。パワハラが黙認されるだけでなく、行為者はパワハラを繰り返しているにも関わらず、重要なポジションに登用されることさえあります。
パワハラが顕在化しない理由の一つは「仕返しが怖い」「正しいことを指摘されている」として、被害者が口を噤んでしまうことです。
パワハラを繰り返す人の多くは、一定以上の役職者であり「仕事ができる」人材であることが大半です。そのため、社内にパワハラ通報窓口が設置されていても、バレたら仕返しされてしまうと考えるのは当然かもしれません。
また、パワハラの被害者は、真面目すぎる性格の人が多く、叱られるのは「自分に原因がある」と考えがちです。その結果、パワハラを申告するどころか、「叱られて当然」だと思い込んでしまう人も多いのが実情です。
つまり、パワハラを撲滅させるためには、企業側が積極的にパワハラの実態を掴む努力を行うことが大切になります。加えて、パワハラが発覚した際には、厳正な対応を迅速に行う体制づくりが重要だといえるでしょう。
企業はパワハラが顕在化しないことにホッとしている?

企業がパワハラの対応に消極的な場合も少なくありません。先に紹介したとおり、企業にはパワハラを防止する義務があります。しかし、実際に対応するとなると多大な労力がかかり、デリケートな対応が求められます。
また、問題が大きくなるとマスコミにも取り上げられてしまうことも少なくありません。さらに、優秀な人材がパワハラを繰り返していると、その対応に企業が及び腰になりがちです。
さすがに、パワハラを隠蔽するブラック企業は激減しているものの、「できれば顕在化しないでほしい」と願っている企業は少なからずあるでしょう。しかし、こうした企業体質がパワハラを横行させているのも事実です。
パワハラを繰り返す人の特徴とは

パワハラを繰り返す人には、共通した特徴がいくつかあります。これらの特徴を把握しておくことで、パワハラを未然に防ぐことも可能です。
ここではパワハラを繰り返す人の特徴を紹介します。自分自身、あるいは周囲の人がこれらの特徴を持っていないか確認してみましょう。
真面目過ぎる
パワハラを繰り返す人は、基本的に真面目です。仕事に対する責任感が強く、中途半端なことが許せないといった人が大半だといえるでしょう。それ故に部下や同僚らの仕事ぶりが気になって仕方がありません。
職場で少しでもフランクな雰囲気が流れると「緊張感がない!」と嫌悪感を示し、態度となって現れます。特に不真面目でなくとも、言動の軽い人に対しては厳しく接することが多く、度が過ぎるとパワハラに発展するのが特徴です。
完璧主義者
完璧主義者の人もパワハラを繰り返す傾向が強くあります。真面目過ぎる人と同様に仕事に対する責任感が強く、小さなミスも許すことができません。何事も完璧でないと気が済まない性分なのです。
そのため一度ミスをした人に対しては、常に懐疑の目を向ける傾向が強くあります。とりわけ、同じ失敗を繰り返す人、成長の速度が緩やかな人に対しては嫌悪感を抱きやすく、パワハラに発展しがちです。
人一倍プライドが高い
パワハラを繰り返す人の多くはプライドが高く、「自分が正しい」と思い込んでいます。確かに正しいことを主張しているのですが、その方法論が間違っていることに気付いていません。
さらに厄介なのは、パワハラの被害者は「正しいこと」を言われているので、「自分に非がある」と思い込んでいることです。そのため、パワハラ案件として取り上げられず、状況を悪化させることも少なくありません。
自分の感情がコントロールできない
パワハラを繰り返す人の中には、自分が行為者であることを自覚している人もいます。こういった人は、後になって相手を傷つけたことに罪悪感を感じ酷く落ち込むことも少なくありません。
しかし、相手が思うように仕事をしてくれないと感情が爆発してしまうのです。自分の感情がコントロールできないのは、メンタル面に問題を抱えていることが大半です。状況によっては早期にカウンセリングを受けさせることが必要です。
過去にパワハラを受けた経験がある
実はパワハラを繰り返す人の中には、自分自身がパワハラを受けた経験がある人も多くいます。本来であれば、自分が受けた苦痛を相手には受けさせたくないと思うものです。
しかし、本人はパワハラだとは思っておらず、これが正しい指導だと考えているので始末に負えません。逆に厳しい指導でなければ「成長できない」とさえ思っています。
人材を育成するには、厳しい指導も必要です。しかし、過度な厳しさは相手に苦痛しか与えないことを改めて教える必要があるでしょう。
基本的に仕事ができる
パワハラを繰り返す人は、基本的に仕事ができることから、往々にして会社から頼りにされています。自分でも仕事ができると自負しているため、仕事ができない社員に対して攻撃的になりがちです。
また、会社側も戦力ダウンを恐れて、指導しきれない場合も少なくありません。しかし、いくら仕事ができてもパワハラを繰り返す社員を放置したままでは、企業としての信用問題に関わります。厳正なる対応が不可欠です。
パワハラを引き起こす社員もメンタルに支障を来している

パワハラといえば、被害者がメンタル疾患に追い込まれることが一般的です。しかし、前項でも触れたとおり、パワハラの行為者も多大なストレスを抱えており、メンタルが崩壊している場合も多くあります。(決して肯定しませんが…)
例えば会社から相当な営業実績を求められている場合、そのプレッシャーに耐え切れず、実績が上がらない社員を罵倒するのは典型的なパワハラの事例です。その他にも、家庭に問題を抱えている役職者が、特定の社員をパワハラの標的にすることも少なくありません。
私は何人ものパワハラ行為者に対峙してきましたが、突然、泣きだす者も少なくありませんでした。抵抗しない者を見つけては、怒鳴り散らすことにより、自分の力を見せつけることで、他の社員を威嚇していたのでしょう。
こういった輩を許すことは企業にとって負の遺産を抱えることに他なりません。しかし、パワハラを繰り返す社員と対応する際には、メンタルに支障が来している可能性もあることを念頭に対応することが大切です。
パワハラを繰り返す社員への対処法

パワハラを繰り返す社員を放置するようでは、企業としての信用を失うだけでなく「法律違反」にもなります。しかし、パワハラ案件は非常にデリケートな問題であり、その対処法に困惑している企業も少なくありません。
ここでは、パワハラを繰り返す社員への有効な対処法を紹介します。自社でパワハラ問題が発生した際の参考としてください。
パワハラであることを認識させる
パワハラを繰り返す社員の多くは自分が「過った行動を取っている」とは思っていません。寧ろ、会社のために尽力していると考えています。また、パワハラを繰り返す人の多くは、間違った主張・指導を行っているわけではありません。
間違っているのは、その「方法」であり、パワハラに対する正しい知識が不足している点です。(暴言・暴力でなければパワハラではないと思い込んでいる。)パワハラを繰り返す社員を更生させるには、その言動が「パワハラ」であることを認識させることが不可欠です。
カウンセリングを受診させるには
前項でパワハラを繰り返す社員の多くは、メンタル面での悩みを抱えていることを紹介しました。過度なパワハラを繰り返す社員の場合であれば、カウンセリングを受診させるのも有効な方法です。
ただし、パワハラを繰り返す社員の多くはプライドが高く、激しく抵抗することも十分に考えられます。そこで、カウンセリングを受診させる際には、まず、パワハラ行為を繰り返していることを認識させることが不可欠です。
過度なパワハラには問責を求める
パワハラを防止・撲滅するのは企業の義務であり、それを繰り返す社員に対しては厳正なる対処が必要です。初回の事案であれば厳重に注意・指導を行い、様子を見ることになります。ただし、一方的に厳しく詰めるのではなく、本人の言葉に耳を傾けることも大切です。
それでもパワハラが繰り返されるようであれば、会社としてのスタンスを示さなければなりません。いわゆる「問責」です。問責を求めた場合、相手方が不服として労働委員会等に申し立てる可能性もあります。
こういったトラブルに対応するには、企業としてパワハラに対する問責の基準を設けておくことが大切です。社内の問責基準(規則)に明記しておくことで、トラブルになった際にも対応がスムーズです。
人事措置を行う
パワハラの被害に遭っている社員を救済するには、当面の措置として人事異動を行うことも検討しましょう。この時大切なのは、パワハラを繰り返している社員を異動させることです。
パワハラを繰り返す社員は「仕事ができる」場合が多く、当該部署やプロジェクトから外したくない場合もあるでしょう。また、パワハラを繰り返す人は周囲にも知れ渡っていることから、受け入れ側から拒否されることもあります。
しかし、被害に遭っている社員を移動させると、組織としての威厳を失います。確固たる姿勢を見せるためにも、パワハラを繰り返す社員を異動させて指導を徹底することが重要です。もちろん、水平もしくは降格人事としなければなりません。
定期的にフォローアップを行う
パワハラを繰り返していた社員には、定期的なフォローアップが欠かせません。もちろん、周囲から近況を確認した上で、本人から現状をヒアリングすることが大切です。パワハラが行われていなければ、慰労の言葉をかけるなどのフォローを継続します。
パワハラが継続しているようであればヒアリングを行い、ここまで紹介してきた措置を講じることが必要です。この時大切なのは、事実関係を丁寧に積み重ねることです。パワハラを繰り返す社員は、徐々に知恵が付いてくることから手口が巧妙になりがちです。
言い訳・言い逃れができないよう、しっかりと裏付けを取ることが不可欠となります。また、単に「悪いこと」として追い詰めるだけではなく、理由を明確にさせることも重要です。
パワハラを繰り返す社員といえども、簡単には辞めさせることはできません。忍耐のいる作業ですが、更生させるのも企業の責務です。
ハラスメントを撲滅するには企業の覚悟が必要

ハラスメントを撲滅するには、企業の覚悟が必要です。ハラスメントを顕在化する勇気が必要です。ハラスメントを顕在化すれば、一時的には世間から大きな批判を受けるでしょう。企業にとって有益な人材を糾弾せざるを得ないこともあるでしょう。
しかし、パワハラが存在する企業に将来はありません。パワハラの加害者の中には助けを求めている人も少なからず居るでしょう。もちろん、パワハラの被害者は一刻も早い「パワハラからの解放」を望んでいます。
もちろん、パワハラの被害者が勇気を出して、顕在化することは必要不可欠です。しかし、立場の弱い労働者に勇気を求めるのは酷です。パワハラの加害者・パワハラの被害者を救えるのは、企業以外にはないことをトップは理解し、覚悟を決めることが重要ではないでしょうか。
この記事のまとめ
- パワハラ防止法には、企業にパワハラを撲滅する責務があることが明文化されている。
- パワハラが顕在化しないのは、被害者が「仕返しを恐れている」「自分が悪い」と思い込んでいるからである。
- パワハラが顕在しないことにホッとしている企業もある。
- パワハラの加害者もメンタルに支障を来している場合も多い。
- パワハラを撲滅するには、企業の覚悟が必要不可欠である。


